そのシステム、止まっても大丈夫?事業継続のためのIT-BCP策定ガイド
「大地震で本社サーバーが停止した」「ランサムウェアに感染し、基幹システムが使えなくなった」。このような事態は、もはや他人事ではありません。ビジネスのIT依存度が高まる現代において、システムの停止は事業の停止に直結します。いざという時に、あなたの会社は事業を継続できるでしょうか?
IT-BCP(事業継続計画)とは、自然災害、システム障害、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、重要な業務を中断させない、または中断しても目標時間内に復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。これは、単なるバックアップ取得や障害対応マニュアルとは異なり、経営的な視点から「どの業務を」「いつまでに」「どのレベルで」復旧させるかを定義する、戦略的な取り組みです。
この記事では、事業の根幹を守るためのIT-BCPについて、なぜ必要なのかという基本から、具体的な策定手順、そして形骸化させないための運用方法までを、わかりやすく解説します。
IT-BCPが必要な理由:現代のビジネスリスク
現代のビジネスにおいて、IT-BCPの必要性は単なる「念のため」ではありません。気候変動による自然災害の激化、サイバー攻撃の巧妙化、パンデミックによる社会情勢の変化など、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。これらのリスクは、もはや「起こるかもしれない」ではなく、「いつ起こるか」という視点で捉えなければなりません。
高まるIT依存度と業務継続への影響
デジタル化の進展により、企業のIT依存度は飛躍的に高まっています。顧客管理、在庫管理、決済処理、コミュニケーション、リモートワークなど、あらゆる業務がITシステムに依存しているのが現実です。この状況では、システムの停止は即座に事業の停止を意味し、収益機会の損失だけでなく、顧客の信頼失墜、法的責任の発生にも直結します。
サイバー攻撃の脅威とランサムウェアの増加
特にランサムウェア攻撃は、近年急激に増加しており、その手法も巧妙化しています。攻撃者は、企業の重要なデータを暗号化し、身代金を要求するだけでなく、データの公開を脅迫するなど、企業に対するプレッシャーを高めています。これらの攻撃は、技術的な対策だけでは完全に防ぐことは困難であり、攻撃を受けた際の対応計画(IT-BCP)が不可欠です。
法的要求とステークホルダーの期待
金融機関をはじめとする規制業界では、BCP策定が法的に義務付けられているケースが増えています。また、取引先企業やサプライヤーからも、事業継続能力の証明を求められることが多くなっています。適切なIT-BCPを策定・運用することは、企業の社会的責任を果たし、ステークホルダーからの信頼を維持するために不可欠です。
IT-BCP策定の3ステップ

効果的なIT-BCPは、「分析」「計画」「運用」の3つのステップで策定・実行されます。
ステップ1:リスクの分析と評価(ビジネスインパクト分析)
まず、自社の事業にとってどのようなITリスクが存在するのか(例:地震、水害、サイバー攻撃、ハードウェア障害)、そしてそのリスクが現実になった場合に、どの業務にどれくらいの影響が出るのかを分析・評価します。この「ビジネスインパクト分析(BIA)」を通じて、優先的に守るべき重要な業務とシステムを特定します。
ステップ2:復旧戦略と計画の策定
分析結果に基づき、重要なシステムを目標時間内に復旧させるための具体的な戦略と計画を立てます。ここで重要な指標となるのが「RTO(目標復旧時間)」と「RPO(目標復旧時点)」です。これらを定義した上で、データのバックアップ方法、代替システムへの切り替え手順(DRサイトなど)、緊急時の連絡体制などを具体的に定めます。
ステップ3:訓練と継続的な見直し
計画は作っただけでは意味がありません。定期的に訓練を実施し、計画の実効性を検証します。システム障害を想定した復旧訓練や、安否確認訓練などを通じて、手順の問題点や担当者の習熟度を確認し、計画を継続的に改善していくことが重要です。
IT-BCPの重要指標:RTO・RPO・MTDの理解

IT-BCPを効果的に策定するためには、業務の重要度と許容可能な停止時間を明確に定義することが不可欠です。ここで重要となるのが、RTO(Recovery Time Objective)、RPO(Recovery Point Objective)、MTD(Maximum Tolerable Downtime)という3つの指標です。
RTO(復旧目標時間)
RTOは、災害発生から業務を再開するまでの目標時間です。例えば、ECサイトの場合、「システム停止から2時間以内に復旧する」といった具体的な目標を設定します。RTOの設定は、業務の重要度と復旧に要するコストのバランスを考慮して決定する必要があります。重要な業務ほど短いRTOを設定しますが、それに応じて復旧体制やシステム投資も大きくなります。
RPO(復旧目標時点)
RPOは、災害発生時にさかのぼって、どの時点までのデータを復旧するかを示す指標です。例えば、「1時間前までのデータを復旧する」といった設定をします。RPOが短いほど、データの損失は少なくなりますが、頻繁なバックアップが必要になり、システムの負荷やコストが増加します。業務の特性に応じて、適切なRPOを設定することが重要です。
MTD(最大許容停止時間)
MTDは、業務停止が継続しても企業が存続できる最大時間を示します。これを超える停止は、企業の存続に関わる深刻な事態を意味します。MTDは、RTOよりも長い時間で設定されることが一般的で、最悪の場合でもMTD以内に業務を復旧させる必要があります。この指標により、災害対策の投資判断や優先順位の決定が可能になります。
クラウド活用で実現する、現実的な災害対策(DR)

IT-BCPの中核となる災害対策(DR)において、クラウドは非常に強力な選択肢となります。自社で遠隔地にデータセンターを持つのはコスト的に困難でも、クラウドを利用すれば、比較的低コストで地理的に離れた場所にデータのバックアップやシステムの待機環境を構築できます。
バックアップ&リストア
最もシンプルなDR構成です。システムのデータをクラウドストレージ(Amazon S3など)に定期的にバックアップしておき、有事の際にクラウド上にシステムを復元します。RTOは長めになりますが、コストを抑えられます。
パイロットライト
データベースなど、システムのコアとなる部分だけをクラウド上で常に稼働させておく構成です。有事の際には、アプリケーションサーバーなどを起動して、速やかにシステムを復旧させます。コストとRTOのバランスが良い手法です。
ウォームスタンバイ/ホットスタンバイ
本番環境とほぼ同じ構成をクラウド上で稼働させておく構成です。有事の際には、即座にクラウド側のシステムに切り替えることができます。RTOは最短になりますが、コストは高くなります。
IT-BCP運用の成功要因と持続的改善
IT-BCPは策定しただけでは意味がありません。実際の災害やインシデントが発生した際に機能するためには、継続的な訓練と改善が不可欠です。多くの企業でBCPが「形骸化」してしまう原因は、策定後の運用・改善プロセスが不十分なことにあります。
定期的な訓練と検証
年に1〜2回の定期的な訓練を実施し、策定した手順が実際に機能するかを検証します。机上訓練(ウォークスルー)から始めて、段階的に実機を使った訓練へと発展させます。訓練では、手順の不備や想定外の問題を発見し、それらを記録・分析して改善につなげることが重要です。
組織横断的な連携体制の構築
IT-BCPは情報システム部門だけの課題ではありません。人事、総務、経理、営業など、すべての部門が関与する全社的な取り組みです。各部門の役割と責任を明確にし、緊急時の連絡体制や代替業務手順を整備することで、組織全体での迅速な対応が可能になります。
技術環境の変化への対応
クラウドサービスの利用拡大、新システムの導入、組織変更など、IT環境や業務環境は常に変化しています。IT-BCPもこれらの変化に合わせて定期的に見直し、更新する必要があります。少なくとも年1回は包括的な見直しを行い、必要に応じて計画の修正を実施します。
IT-BCPの国際規格とコンプライアンス
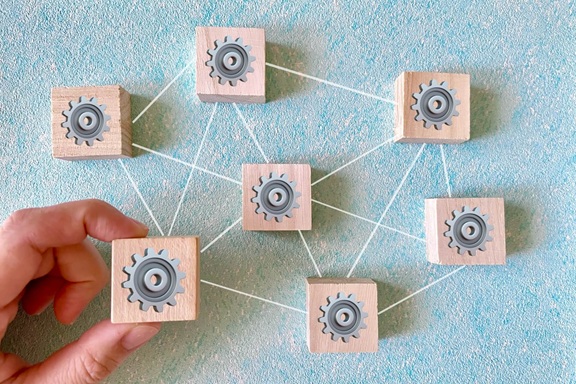
IT-BCPの策定においては、国際規格や業界スタンダードへの準拠が重要な要素となります。特に、グローバルに事業を展開する企業や、規制の厳しい業界においては、これらの規格やスタンダードへの適合がビジネス上の必須要件となっています。
ISO 22301(事業継続マネジメントシステム)
ISO 22301は、事業継続マネジメントシステムの国際規格で、世界的に幅広く採用されています。この規格では、リスクアセスメント、ビジネスインパクト分析、事業継続戦略の策定、そして定期的な訓練と見直しの実施が求められます。IT-BCPの策定においても、これらの要求事項を満たすことで、国際的な信頼性を得ることができます。
NISTサイバーセキュリティフレームワーク
米国国立標準技術研究所(NIST)が開発したサイバーセキュリティフレームワークは、「特定」「防御」「検知」「対応」「復旧」の5つの機能から構成されます。IT-BCPにおいては、特に「対応」と「復旧」の機能が重要であり、インシデント発生時の適切な対応手順や復旧プロセスの確立が求められます。
金融業界のコンティンジェンシープラン
金融業界では、各国の金融当局が事業継続計画の策定を義務付けており、特にシステミックリスクやサイバーセキュリティリスクへの対応が強化されています。日本では金融庁の監督指針やガイドラインに基づいて、金融機関は定期的なシステムリスク評価やコンティンジェンシープランの更新を実施することが求められています。
IT-BCPの実装と組織革新
IT-BCPの成功は、単に計画書を作成することではなく、組織全体の意識と行動を変える組織革新の一環として捉えることが重要です。危機管理の文化を組織に根付かせ、各部門が主体的にリスク管理に取り組む体制を構築することが、持続的なレジリエンス向上につながります。
リーダーシップとコミットメント
経営トップのIT-BCPに対する強いコミットメントは、組織全体の取り組みを左右します。経営層は、IT-BCPを単なるコストセンターではなく、企業価値を守るための戦略的投資として位置づけ、必要な人的・財務的リソースを継続的に提供することが求められます。また、定期的なレビューや訓練の結果を経営会議で報告し、継続的な改善を促進することが重要です。
部門横断的なコミュニケーションと連携
IT-BCPの実効性を高めるためには、情報システム部門だけでなく、全部門が連携して取り組むことが不可欠です。特に、人事、総務、法務、広報などの部門との連携体制を事前に構築し、緒急時の役割分担やコミュニケーション手順を明確化しておくことが重要です。定期的な連絡会議や合同訓練を通じて、部門間の連携を強化し、組織全体のレジリエンスを向上させることができます。
継続的学習と適応
IT-BCPは一度策定したら終わりではなく、継続的な学習と適応が必要です。新しい脅威の出現、技術の進歩、ビジネス環境の変化などに応じて、定期的にリスクアセスメントを更新し、必要に応じて計画を修正します。また、他社のインシデント事例や業界のベストプラクティスから学び、自社のIT-BCPのさらなる強化に活かします。
事業継続は経営課題。TechThanksの伴走支援
IT-BCPの策定と運用は、情報システム部門だけの課題ではありません。どの業務を優先し、どこまでのコストとリスクを許容するのか、という経営判断が不可欠です。TechThanksは、単に技術的な解決策を提示するだけでなく、お客様の事業内容や経営方針を深く理解した上で、最適なIT-BCP策定を支援するパートナーです。
ビジネスインパクト分析から、RTO/RPOの策定、クラウドを活用した最適なDR構成の設計・構築、そして定期的な訓練の企画・実行まで、お客様の事業継続を強力にバックアップします。また、国際規格や業界スタンダードへの準拠を支援し、グローバルな信頼性を持つIT-BCPの構築をお手伝いします。
「何から始めればいいかわからない」「BCP計画が形骸化してしまっている」。そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひTechThanksにご相談ください。お客様のビジネスに寄り添い、実効性のある「生きている」IT-BCPを共に作り上げていきます。